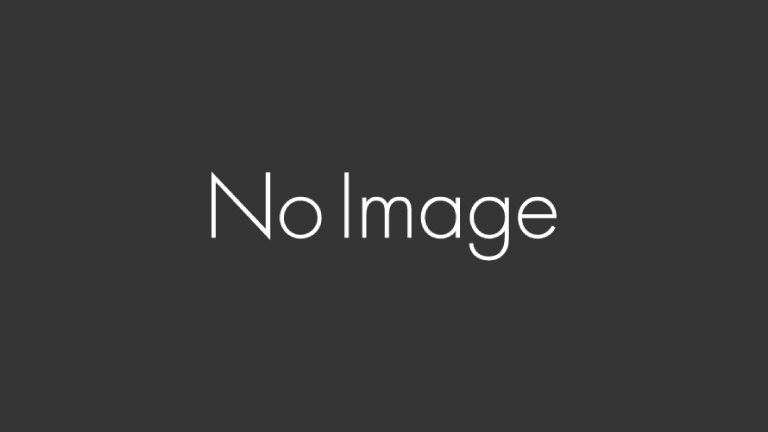当然ながら下りは登山の後半です。
疲労は蓄積されています。
そして夕暮れというタイムリミットがあります。
下りには、安全であることはもちろん、
疲れないこと、遅くないことが必要です。
私は下りの方が断然好きです。
下りが苦手な人は結構います。
自分の経験から下りを考えてみました。
なるべく下方への移動を完全には 止めない。
下ろした左足に体重が乗ってきたときに右足は次の場所に下ろす。
うまくいけばその右足に体重を乗せながら左足を次の場所に向かって下ろす。
何も考えず一歩下りるのではなく2歩、または3歩をどう下るかをいつも考えます。
下方への移動を止めるたびに足に負担がかかります。
止まるのですから時間も無駄になります。
膝と足首を柔軟に使い上体が階段状ではなく直線的に移動するよう意識します。
無理なように思えるかもしれませんが、すぐになれます。
視線を一歩先ではなく二、三歩先に走らせるのは理にかなっています。
一歩を下す場所は次の一歩を下すのに都合よい場所であるべきです。
人間の脳はそれくらい簡単にやってのけます。
以前TV で羽生善治4冠が「途中分岐する変化まで統合すると300~400手先まで読む」と語ったように
人間の脳は先読みが得意なのです。( 私は将棋は全然分かりませんが )
もちろん危ないと思ったりした一歩は十分に慎重に一歩を下します。
上体は真っすぐに
重心は常に両足の真ん中に意識します。
足が万一滑っても尻もちになります。
尻もちがブレーキになり手が自然に何かを掴んだりもします。
前かがみは絶対にダメです。
滑ってお尻を着いた拍子に前側に落ちる可能性があります。
前側には掴むものは何もありません。
そして着地する場所はかなり下になりしかも下り斜面です。
想像しただけで恐ろしくなります。
滑らないためには頂点を踏みます。
斜面は滑る可能性があります。頂点は斜面ではないので滑りません。
たとえ濡れてつるつるな石でも正確に頂点を真上から踏めば滑りません。
登山靴の靴底の硬さはこのためにも必要なのです。
面を踏む場合下り傾斜の面は踏んではいけません。
おおざっぱでもいいですから斜面の傾斜にも注意を払います。
それだけで尻もちをつくことは大幅に減るでしょう。
濡れた木の根はなるべく踏まないようにします。
一つは自然に対する遠慮というか配慮です。
もう一つは、木の根は頂点が線のようなもので
枯れた根の場合など、その方向に唐突に滑ることがあります。
まとめ
下りは、一歩一歩ただ下りるのではなく、二歩、三歩をどのように下るのかを考えることが必要。
重心は両足の真ん中に置き上体は絶対前に倒さないこと。
靴底が踏む場所は頂点が良い。