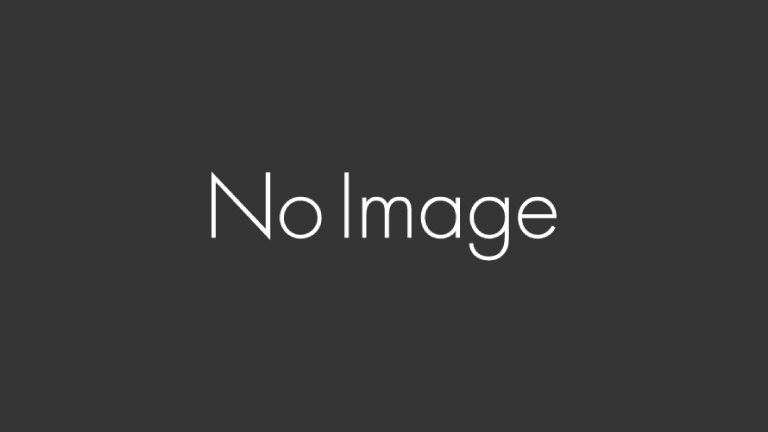プロである林業従事者の事故率は他の業種の10倍を超える。
林業は危険な職業なのです。
私たち素人はできるだけプロの知識と経験を学ぶべきなのはもちろんです。
その上で、私たちはプロとは違う行動をとらなければならないのです。
その根拠となる統計数字があります。
林業従事事故死の80%が50歳以上というデータがあるのです。
高齢化によるものだけでは説明できない数字です。
素人が急斜面での大倒木の処理を小さなケガもなく終えることができた。安全のヒントになるのでは?
私たちがやったことは
チェンソー作業について、ネットで調べまくった。
キックバックの怖さだけでなく、発生のメカニズムも学びました。
様々な危険についても学びました。
そして、自分でそれらを学んだ人だけがチェンソーを扱いました。
はがらしをやった
倒木を何もせずそのまま放置しました。
そうすることで水分が抜け軽くなり
倒木もその状態になじんで安定するらしいです。
ただ私たち素人には軽くなったとの実感はなかったですが。
枝葉を全部取り除いた
最初に大量の枝葉で状況を把握できないまま切断しようとして、
チェンソーが挟まれて大変な目にあいました。
それに懲りて視界を遮る枝葉を徹底的に取り除きました。
これにより判断が正確に行われるようになりました。
切り落とす一つ一つの質量をなるべく少なくした
危険のほとんどが樹木の重さによるものです。
生の木を水に浮かべてみるとほんのわずかしか浮きません。
樹木はほぼ水の重さと同じなのです。
直径15センチで1メートルの丸太は
7.5×7.5×3.14×100=17663。約18キロの重さがあるのです。
水で言えば18リットルでストーブ用の灯油のポリタンクがその容量です。
結構な重さで、しかもそれは硬いのです。
小さく少しずつ切り落としました。そうすることで重いことからくる危険を減じました。
徹底的に怖がった。
跳ねたり裂けたり転がりだしたりを徹底的に怖がって用心しました。
判断がつかないときには少しだけやって様子をみました。
手間ひまを十分にかけた
根がえりした木の処理では上部の根と土を取り除いてから切断しました。
大変な時間と手間を掛けました。
チェンソーは同時に二つを動かすことを禁じた。
チェンソーは大小の二台ありました。
一台だけを動かすことにしたのは複雑化や混乱を嫌ったからです。
それと切断とその結果予想される危険に全員の注意を向けるためです。
プロとは違う安全に対するアプローチが必要です。
自分でも驚いています。素人の私がこんなことを書いているのですから。
しかし、最初に書いたように現実にプロの方々の怪我や死亡率は驚くほど高いのです。
当たり前ですが私たち素人は絶対に死んだり怪我をしてはならないのです。
ということは、必然的にプロとは違う方法、アプローチをとるしかありません。
プロよりも勉強し研究し調べまくる
素人はプロのように時間をかけて現場での経験を積むことができません。
読んで、見て、聞いて、たくさんの疑似体験をすべきです。
死ぬ可能性のあることを経験から学ぼうとするのは怖すぎです。
むしろプロよりも勉強すべきです。官製の数時間の講習では足りないでしょう。
現場作業の経験だけではわからない力学的考察やメカニズムも知るべきでしょう。
時間をかける。考えまくる。
プロの事故が後を絶たないのは、職業として効率などの経済性を無視しては成り立たないからです。
私たち素人は十分な時間をかけ、観察をして方法を一つ一つそのたびに考えるべきです。
少しずつやることです。
そして無理ならやめることです。それができることが最高の強みでしょう。
複雑化を避ける
一つ一つかたずける。
見えなければ見えるようにする。
切断と片付けのような2種類の作業を同時にやらないようにする。
チェンソーは一台だけを動かす
二台以上だとついついいつの間にか何らかで張り合うことになる。
危険予測の判断が複雑になる。
切る人と危険を危険を察知し避ける人の二役をすることになってしまう。
また背後にエンジン音がするだけで集中力はそがれる。
怖がる
プロは怖がってばかりでは仕事にならない。しかし私たちはおっかなびっくり全てをやらなければならない。